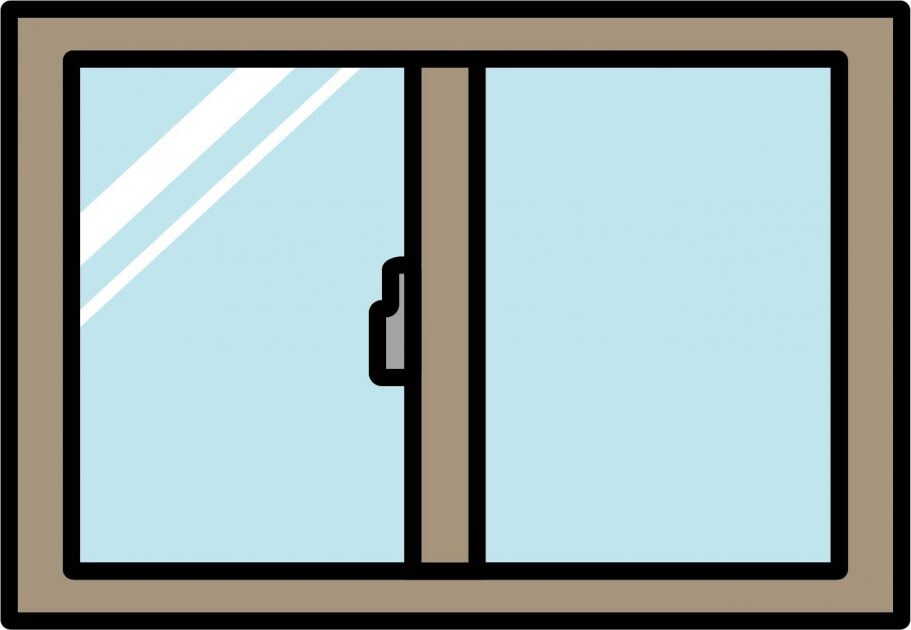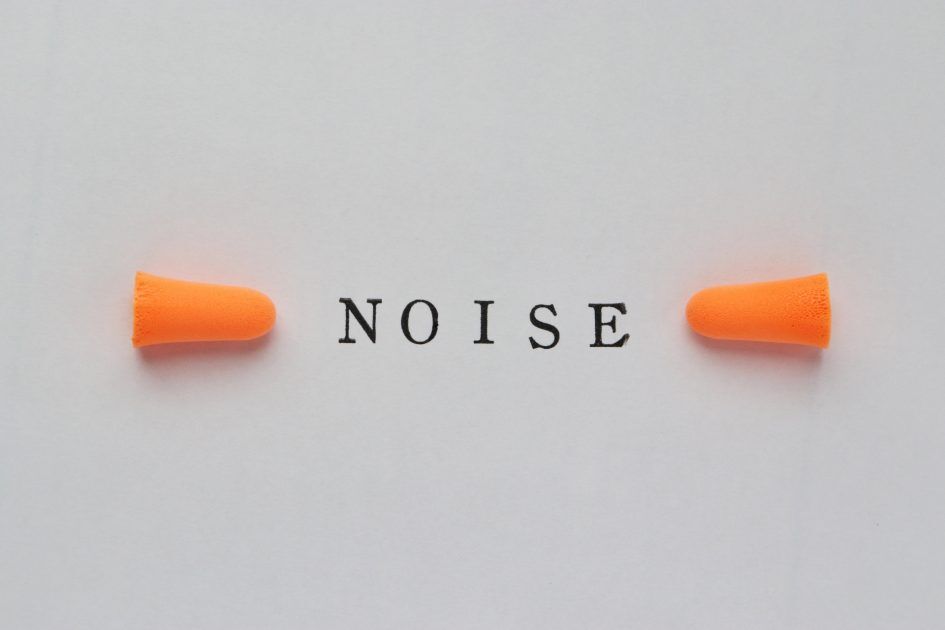この記事は、こんな方に向けて書いています。
・照明の基本が知りたい
・照明の情報は、どうやって集めたらいい?
心構え
照明は、「暮らしやすさ」や「住み心地」を決める大切なポイントです。
「間取りの打合せでヘトヘトで、着手承諾まで時間もなかったので設計士さんの提案のまま決定」ではもったいありません。
間取りの検討を終えて照明の検討に入る段階では、ひと山超えた疲労感・達成感で脱力状態になりやすいので注意が必要です。
照明を成功させるコツは、ズバリ「気力・集中力」です。間取り検討が終わっても気を抜かず、照明の検討が終わるまで走り切りましょう。
照明の基本
おすすめは分散照明
照明の検討をはじめる段階では、ほとんどの人は基礎知識がありません。
【照明の基本】
・照明配置の基本的考え方
・光の色の使い分け
・電気図面の読み方
・スイッチの種類と活用
まずは、「照明配置の基本的な考え方」を知る必要があります。
照明を考える上での基本的な考え方は、照明メーカーによっていろんな言い方がされています。
たとえば、Panasonicの場合は「タスク&アンビエント」という言い方をしています。
タスクは、食事や勉強、作業をするときの手元灯です。アンビエントは「周辺」という意味で、まわりの明かりです。
言い方は違っても、各メーカーとも言っていることは同じです。
一か所に集中せず適度に光源を分散させる「分散照明」をしましょう、ということです。
天井にシーリングライトがひとつだけの部屋をイメージしてみてください。平板で奥行のない、均一な印象の明かりになります。
次に、部屋の中心にペンダントライトがあって、周辺にダウンライトがほのかに壁を照らしている部屋をイメージしてみてください。
明暗のメリハリがついて、ぐっとリラックスできる空間になります。
ぜんぶの部屋を分散照明で計画すると結構なお値段になるので、子供部屋はシーリングライト一つ、LDKは間接照明というようにメリハリをつける方法がおすすめです。
照明器具の明るさ
ダウンライトには、明るさの違いで「100形」と「60形」があります。
| タイプ | 設置の目安 |
|---|---|
| 100形 | 2帖に1個 |
| 60形 | 1.5帖に1個 |
Panasonicのカタログには、60形は1.3帖に1個とありますが、ざっくり1.5帖で考えて問題ありません。
ダウンライト以外は「lm(ルーメン)」でカタログ表記されます。300~600lmで1帖分と考えましょう。
数値に幅があるのは、部屋によって適度な明るさが違うからですが、れんきちは 400lm=1帖分 で考えていました。
明るさの単位には、lmのほかにlx(ルックス)があります。ルックスは光があたったモノの表面の照度、ルーメンは照明器具自体が発する照度です。
| 種類 | 何を表しているか |
|---|---|
| lm(ルーメン) | 光があたったモノの表面の明るさ |
| lx(ルックス) | 照明器具自体が発する明るさ |
| K(ケルビン) | 色味(赤・黄色~青・白) |
明かりの色
明かりの色は「電球色」「温白色」「昼白色」に大別されます。
もっと細かい区分がありますが、マイホームの照明計画では、この3種類でおさえておけば問題ありません。
「K」は、色味を表す単位の「ケルビン」です。この数値が小さいほど黄色っぽく、大きいほど青っぽく見えます。
| 種類 | 色味 | 特徴 | おすすめの利用 |
|---|---|---|---|
| 電球色 | 2,700K | あたたかい くつろぐ色 | LDK |
| 温白色 | 3,600K | 中間色 | オールマイティー |
| 昼白色 | 6,500K | モノの色判別 がしやすい | WIC・ キッチン手元灯 |
一条工務店では、最近「温白色」を標準で選択できるようになりました。
温白色は、オールマイティーで、とっても使い勝手のいい色です。迷ったときは温白色にしておいて間違いないです。
れんきち宅でも、温白色を多用しています。
たとえば夜帰ってくるときは電球色でリラックスしたいけど、朝は仕事(学校)モードにしたいので、玄関ホールは中間色の温白色を採用しました。
キッチンの手元灯もダイニングの電球色とケンカしないよう、温白色を採用しました。
検討しよう
カタログを入手
照明の基本を勉強するのにいちばん効率的なのは、メーカーのカタログを見ることです。
発行が2018年と少し前になりますが、Panasonicの「すまいのあかり設計集 2018 基礎編」が神本です。部屋ごとの照明の基本が過不足なく載っているので、これ一冊を読み込めば大丈夫です。
吹き抜けがある場合は、プラスしてDAIKOの「吹抜照明」をプラスして読むことをおすすめします。吹抜けは高いところから照らすので、床から離れるとどれくらいの明るさになるかを理解しておく必要があります。
「明るさは、距離の二乗に反比例する」っていう、最初聞くと「?」なことを、イラスト入りで分かりやすく解説しています。
最後に、Panasonic製品を計画している人向けに、もうひとつカタログを紹介します。「住宅用照明器具Expert2020」という1,000頁を超える冊子です。
web版もありますが、紙版の方が圧倒的に使いやすいです。Panasonicのショールームで紙のカタログをもらってきましょう。
題名がExpert だし分厚いので事業者向けカタログかなと最初は思いましたが、検討を進めるときに本当に重宝しました。結構使い込んだので、最後には、付箋がいっぱい付きました。

この冊子Expertは、設計士さんは、みんな持ってるみたいだね
お得なキャンペーン
一条工務店には、「LED照明で省エネ・節電キャンペーン」があります。
製品と工賃込みで、「3,000円/坪 × 施工面積」というお得な価格設定です。家は明るければいいという人は、このキャンペーンの対象製品で揃えれば格安に計画できると思います。
キャンペーンを使いつつ、ポイントで対象外のお気に入りをチョイスすることもできます。
ただ、照明の積算のルールが複雑で「この計画だったら、キャンペーンを使うのと使わないのでどちらが安いのか?」が簡単にはわかりません。
採用したい照明が決まった段階で、キャンペーンを使う場合と使わない場合で積算してもらいましょう。
ここで、半額で入れることができる4社を覚えておきましょう。
Panasonic|オーデリック|コイズミ照明|DAIKO(大光電気)
Panasonicがメインになる場合が多いと思いますが、他のメーカーでお気に入りの照明があれば考えてみましょう。

れんきち宅のダイニングのペンダントライトは、Panasonicが条件・好みに合わずオーデリックを選択したよ
まとめ
照明の検討を始める段階では、みんな基礎知識ゼロです。紹介したカタログなどで、いろはの「い」をインプットするだけでも、そのあとの検討がずっとスムーズになります。
間取りがバッチリでも、照明がイマイチだと、せっかくの「家づくり」も台無しです。
照明は、「暮らしやすさ」や「住み心地」を左右する重要なポイントです。くつろいだり、勉強したりというシーンに合わせてうまく照明を計画しましょう。
基礎がわかれば、次は部屋ごとの具体的な照明計画ですね。トイレ・玄関の照明については、こちらがよく読まれています。